“志々の國”づくり
●背景
政治が混沌としています。
日本だけではなく、世界全体です。
いま、アメリカのウォールストリートから始まった「1%の金持ちによる支配 終わらせよう」というデモが全米に、そして、全世界に広がってきています。
並行するように、ギリシャの財政破綻から、再び現れ始めた世界金融危機の恐怖も膨らんできています。
長い時間をかけてやっと自然が創りだした化石燃料が出る土地を、また、森林の茂る土地をたまたま所有しているというだけで、それらの天然資源を個人の利益として売り払っていいのでしょうか?
土地の所有者が、群がる巨大資本とともに、自然が蓄えてきた資源をあっという間に私的利潤の形で変えながら、地球温暖化と地域紛争を引き起こしています。
何とかしなければならないこれらの不条理を止めさせる力が今の世界には、存在していません。
このような国境を越える問題を解決する力をつくり出せていない今の世界の政治状況。
今の国民国家の連合の力では、なし得ない事柄に関して、一日も早く、国を超える公権力をつくり出さなければならないと思います。
●「物語」と「尊厳」
そもそも、公権力をつくる目的は、社会集団として「生存し続けること、抹殺されないこと、社会を永続させること」に集約されます。
従って基本政策も、生存し続けるために「食料とエネルギーを自給」し、 抹殺されないために「自衛力」をもち、 自分たちがつくり出した社会を支える自然と土地を守るための誇りと使命を維持する「教育と訓練」をなすこと、この3点に集約されます。
これから求める公権力は、“玉(ぎょく)”が真ん中にいる国ではなく、“域”が真ん中にある國(クニ)。
その國(クニ)はその地域の過去と未来の「物語」にもとづき明確な“正義”を持ち、その“正義を実現する志”をもつ國(クニ)です。
もちろん、信仰が語られ、道徳が語られる國(クニ)です。
そして、他の個人の、他の國(クニ)の描いてきた「物語」と、また、これから描こうとしている「物語」づくりの“意志”を「尊厳」として認めあう個人が生活する社会です。
いま求めるべき社会規範は、「自由主義」を超えた「尊厳主義」です。
現代社会形成に重要な規範となってきた「自由主義」は、個人や、集団の自由を最上段に掲げるために、一歩踏み込んだ“社会正義”を曖昧にして来ました。
自由に振る舞えば「見えざる手」が最上の帰結をもたらしてくれる。自由市場が神の手の働きを導いてくれる。
しかし、今われわれの目の前にもたされた「自由主義」の帰結は、「1%の金持ち社会」であり、誰も責任を取らないですむ無責任体制であり、頻繁に起こる経済と自然の暴走による“怯え”でしかなかったのです。
「自由主義」に基づく競争で、豊かさだけの序列によって勝ち負けを決める社会から、一人ひとり、一つひとつの意志が紡ぎだす「物語」を大切にする「尊厳」第一の社会を築かねばならないのです。
●「意志」に基づく公権力づくり
必要な公権力は私たちの「意志」によってしか形成できません。
また、強い意志の大きな連帯があれば、必ず私たちの求める公的な力はつくり出しえます。
昨年スイスに行き、スイスの半直接民主制と地方制度を学ぶ機会がありました。
その最大の収穫は「意志の国(Nation of Will)」という言葉との出会いでした。
スイスは、神聖ローマ帝国からの「自由と自治」の「意志」に基づいて創り出された、言語や文化を超えた「意志の国」であるとの「物語」でした。
確かにその歴史を読むと、原初は3つの都市経済圏が連帯し、大きな権力に抗して自立を保つという「意志」が、時間とともに他の地域も惹きつけ、いまの4カ国語が話されるスイスが形づくられています。
私たちも “怯え”ではなく“安らぐ”ことができるこれからの「物語」をつくるという強い「意志」で、言葉さえも超える必要な公権力をつくり出そうではありませんか。
大英帝国がつくり出した「連邦(commonwealth)」という言葉があります。
英字だけ読むと「共通利益」となりますが、アダムスミスの国、イギリスが旧植民地諸国を利益(wealth)の連邦として統合する時に使う言葉です。
これに習って、同じ志のある國(クニ)が連帯して、共有できる「意志」に基づく連帯國(Common-Will:共通の意志)をつくる“志々の國”づくりを国を超えて行うことを考えています。
“志々”としているのには、各地域のいろいろな志の「尊厳」を認めた上で、連合すること、そして、國(クニ)の領域が「意志」に基づいて幾つも重なってくることをイメージしています。
こう考えると、何ともやりがいのある公的な力づくりだなと思えてきます。
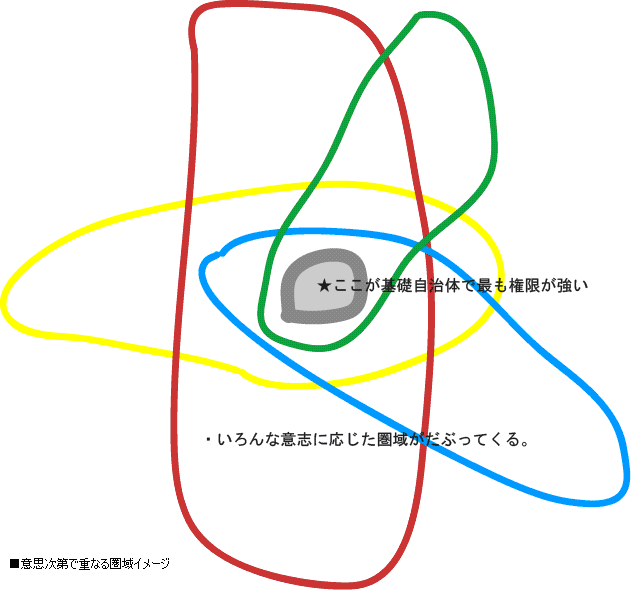
もちろん、公権力をつくるためには、大きな作業も控えています。
憲章をつくって、代理人による議会と、住民の直接参加の機会と、執行機関、司法機関、徴税権、強制力(武力)を準備するなどが考えられます。
しかしまずは、あまり遠くを見ず、福岡から国を超えた公権力を語りあう「“志々の國”世界会議」”Forum for Force of Common-Will”、を始めたい。
社会づくりに共通の意志を持つ地域(自治体)が、個人が、いまの公権力の枠を超えて、連帯する仕組を考える会議を国を超えておこないたい。
ここから新たな国家、国家連合、あるいは、「基礎自治体最上位」の世界システムをつくり始めたいと思っています。
●スイスをモデルに
まずはスイスをモデルとして、考え始めます。
従って;基礎自治体が最上位、州や国が決めても自治体が認めなければそのルールは不適用。住民発議・住民投票が公的に公正に執行。
半直接民主制、即ち、代議員制と住民直接参加の並立。
代議員は原則、ボランティアとし、政治が常識から遊離しない。
できるだけ議会に予算をかけない。不毛な政治的駆け引きによる停滞を許さない。
代議員の定数削減とともに、住民直接参加を拡大させながら、最終的には全員ボランティアへ至る。
などなどのイメージが浮かんできます。
スイスでは、住民の直接参加が多い自治体ほど財政赤字が少なく、一人当たりの所得も高い。
スイスは、今でもランズゲマインデという、みんなが集まってその場で投票する地域議会がまだ残っています。
まずは、この「直接参加の議会」をやってみたいなと思っています。
私たちの力を集めましょう。

