今、アメリカでは、「エコノミック・ガーデニング」、市域全体を庭園のように考え、その中に存在している企業を草木と考え、その企業ひとつひとつを草木一本一本のように、丁寧に育てていく。
地形に、気候に、インフラにふさわしい、地域に根ざした経済振興策が広がりを見せてきています。
大樹の下に、中木、低木、そして草花まで育てて、大きな生態(エコ)としてのエコノミーをつくりあげる。
一時国が勧めていた産業クラスターづくりのような、学校、研究所から、インフラまで含めた大経済政策ではなく、もっと単純に、伸びている企業や商品をとにかく育てる。
支援する前提はノウハウをオープンソースとして誰でも参入できる競争下に置き、群として事業を育て、企業を育てる。
具体的で、大きな雇用力を育てる施策です。
【提案1】
 |
福岡での経済活動を他都市よりも確実なものとするためのデータ整備
 |
経済振興のための事業がたくさんあるのですが、その成果を測るデータが、国による少し遅れたものでしか準備されていません。
政策によってどれだけ目標を実現できたかをリアルタイムで確認することが出来ないのです。
リアルタイムでのデータ整備を質問しました。
国の仕組を理由にして、福岡ではどうしようもないと言うのは止めにすべき。
計算法が公開されているならば、それを基に、統計学的に幾つかのデータを入力する程度で比較的容易に、ある程度信頼できる速報値ぐらいは算出できる。
経済の実態を他よりもいち早く把握し、どこよりも早く経済を先導していく。
先んじることで新しい経済の流れを呼び込む機会が拡大すると述べました。
福岡では的確なマーケット情報がないまま、思惑だけで不動産投資が進んだ結果、今年の基準地価下落率は全国でも最悪を記録ました。
実態にそぐわない地価の高騰は、大きな痛手を経済に与えます。
公的に福岡市のマーケット情報を整備し、誰でも使えるようにすることによって、投資も安定するし、経済政策も確かなものとなる。
地域のマーケッティングデータを公的に提供していただくことを要望しました。
さらに、企業ひとつひとつを指導していく、商品ひとつひとつを売り込んでいくためには、マーケッティングが解った専門家の力を借りなければなりません。
専門家によるアドバイス、データアクセスを公的事業として肩代わりし、情報とアドバイス提供を政策としておこなっていくことを提案しました。
利便性が高い地下鉄野芥駅周辺に早期設置する。
【提案2】
 |
伸びているサービス・商品をもっと伸ばし、雇用力を高め、独自産業として育て上げる
 |
経済が収縮し、その構造変化を迫られている現状の中で、唯一確かな、経済振興施策は、のびている企業・商品をのばすことだと思います。
言い換えると、私たち一人一人が支持している、すなわち、現時点で売れているモノ(内需)をのばし、結果としてその分野の雇用を拡大させ、その分野の企業集積を図り、その地域の主力産業としていくことです。
伸びている企業・商品の支援策としては創業支援からセカンド・ステージ支援へ、施策の重点を移すべきです。
さらに、企業の大きさや歴史などによらず、とにかく、市民の支持が高い商品をどんどんのばしていく政策を行うべきです。
博多明太子は、商品を開発した人が、特許などせずに、製法をオープンにして、誰でも参入でき、競争できるようにしていたので、これだけの産業に成長したのです。
決して“たらこ”や“唐辛子”の産地だったわけではない。作り方をオープンにして、他でつくっていない売れる商品をつくり、それをみんなで食べ続けただけなのです。
売れる商品を競争下でつくらせて、自発的な改善のサイクルを定着させ、競争力のある企業群をつくりあげる。
のびている商品を大樹に育て、その下に、中木、低木、そして草花まで育てて、大きな生態(エコ)としてのエコノミーをつくりあげる。
単純に、伸びている事業や商品をとにかく育てる。
支援する前提はノウハウをオープンソースとして誰でも参入できる競争下に置き、群として事業を育て、企業を育てる。
具体的で、大きな雇用力を育てる施策です。そのような観点から、群としての企業・商品をつくりあげることを提案しました。
【提案3】
 |
事業効果を指標化し、予算“1円”、“1円”が同じ効果を上げるように配分する
 |
経済振興局の平成20年度の37の事業に関して、成果指標をあえて決めてもらい、その成果と予算額の大きさが適正なのかを考えました。
例えば、企業誘致にも、創業支援にも予算配分しているのですが、その配分額が適正であるか、果たしてどちらも必要なのか、どちらを優先すべきか、ということです。
これまでの政策は、国の事業メニューが提示され、その中から補助金を取れるのをやるというのが、自治体の政策でした。
地方主権で政策を作り上げることが求められている今、地方で独自に指標を設定し、その指標の動きを見ながら、予算配分を適正化していくことが必要です。
そこで提案しました。
ある年度、例えば2001年の時点での成果指標をすべて100とする。
例えば、ある事業の指標が8件、別の指標が121万人であっても、おしなべて100として、各指標を作る。
そうしたら、その指標の100からの変化の具合で成果を他の事業と比較出来るようになる。
ある事業は成果指標が80に下がっている、ある事業はそれが150に上がっている。
予算規模が同じならもちろんどちらに、“1円さん”を振り向けるかは明らかです。
さらに、100でそろえた指標を決算額で割る、一円当たりの効果(“1円さん”がどれだけ働いたか)を各事業で比較する。
そうしていくと事業間の予算効果が比較できる。少し、詳しく述べると、まず、“1円さん”ひとつひとつが、どれだけの成果指標を獲得しているかを見る。
そして、成果指標獲得数が少ない、遊んでいるかもしれない“1円さん”を、働き過ぎ、たくさん成果指標を獲得している“1円さん”の手伝いに向ける。
言い換えると、どの“1円さん“も、平等に働くように、再配分する。
そうして、初めて予算の1円1円が、平等に有効に働く状態で、そこで最大の予算効果を実現する状態に成るのです。
「“1円さん”に平等を!」が予算の配分のポイントになります。
【結び】
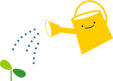
現状では決算の議論は、予算を無事に執行したかどうかで止まっています。
適正な予算執行がおこなわれているか、きちんと市民へ伝わっているのか心配です。
きちんと成果指標をつくり、成果と予算規模が適正であるかを確認することが出来るデータと作業環境を整えることが急務だと思います。

